日本企業がインドネシアに進出する際に、インドネシア人・企業をパートナーとして、合弁会社(Joint Venture: JV)を設立することが多いように思います。
一般に、海外進出に際しては、独資(日本企業100%出資)での進出がよいと言われており、私も、以前に出席した弁護士会主催の海外進出セミナーでは、そのように聞いておりました。
しかし、インドネシアにおいては、必ずしも、独資が望ましいとは思えず、信頼できる有力なインドネシア人パートナーを見つけ、その方にインドネシア法人の株式の一部を保有してもらう方がいいのではないかと考えています。
1 合弁会社のデメリット・リスク
もちろん、合弁会社には、以下のようなデメリットやリスクが存在します。
(1)意思決定に要する時間
まず、独資ではないため、意思決定に時間を要します。特に、経営方針に相違が生じてきた場合には、株主総会、取締役会での意思決定ができなくなる事態もあり得ます。
特に、業務拡大時、又は業績悪化時において、追加投資が必要となる場合でも、インドネシア人パートナーの理解が得られず、機動的に増資できなくなるということが起こり得ます。
(2)インドネシア人パートナーとの法的紛争の可能性
また、インドネシア人パートナーと、合弁会社の経営権をめぐって、法的紛争が発生するというリスクもあります。
他方で、独資の場合、法律上、(インドネシア人パートナーの意見を考慮する必要がないため、)会社経営が行いやすく、インドネシア人パートナーに合弁会社を乗っ取られるというリスクも、法律上は考えにくいです。
ここで、「法律上」と書いたのは、法的にはインドネシア人パートナーの意見を無視できても、事実上は、インドネシア人パートナーの意見を取り入れないと、円滑にビジネスが進まないことが多いからです。
2 合弁会社である必要性・メリット
インドネシアに進出するに際して、インドネシア人パートナーと合弁会社を設立している日本企業が多く存在します。
(1)合弁会社設立の必要性(外資規制)
その理由の一つとして、インドネシアの外資規制があります。
特定の業種では、外資の出資比率に上限が設定されているため、そのような業種では合弁会社を設立する必要があります。
外資規制を定めた法令は、 「投資分野において閉鎖されている事業分野及び 条件付きで開放されている事業分野リストに関する 大統領規程 2016 年第 44 号」です。
英訳: PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 44 YEAR 2016 CONCERNING LISTS OF BUSINESS FIELDS THAT ARE CLOSED TO AND BUSINESS FIELDS THAT ARE OPEN WITH CONDITIONS TO INVESTMENT
その後、上記大統領規程は、「投資事業分野に関する大統領令2021年10号」(ジェトロ仮訳)により撤廃されました。また、この改正令として、大統領令2021年49号が出ております。
具体的な規制対象業種は、同法令添付のリスト(大統領令2021年10号リスト:ジェトロ仮訳)に掲載されています。
ネガティブリストは、インドネシアの経済情勢等を踏まえて、定期的に見直しが行われます。現在のネガティブリストは、2016年5月に制定されたもので、昨年より、一部業種を対象に、改正の話題が上がっているものの、現時点では改正されていません。
※前述のとおり、大統領令2021年10号により、改定されました。
大統領選挙も終わったことなので、今年あたりに改正があるかもしれませんね。
余談ですが、私が、在インドネシア日本国大使館で外交官をしていた頃には、日本企業に影響のある規制の緩和や改悪防止に向けて、インドネシア政府の関係省庁 (外資規制の場合だと、投資調整庁(BKPM)や経済担当調整大臣府など) を回ってロビーイングを行っていました。
当該規制緩和がインドネシア経済に与えるメリットを説明したり、逆に当該規制がインドネシア経済に与える悪影響を説明し、当局に再考を促したり、また時には国際法的視点から、当該規制の国際法違反の可能性を指摘するなど、あらゆる方向からインドネシア政府に説明し、日本企業がインドネシアでのビジネスを行いやすくなるようなルール作りに向けて、ロビーイングを行っていたのが懐かしいです。
話を戻しますが、製造業などネガティブリストに掲載されていない業種では、外資100%での会社設立が認められているので、必ずしも合弁会社を設立する必要はありません。
しかし、このような場合でも、信頼できる有力なインドネシア人パートナーを見つけ、一定数の株式を保有してもらい、合弁会社として共同でビジネスを行っていくことをお勧めします。
日本企業が独資100%で会社を設立することは法的に可能ですが、その後のビジネスを考えると、インドネシア人パートナーの関与・協力が大切だと思うからです。
(2)合弁会社のメリット
・当局とのコミュニケーション
インドネシアでは、ビジネスを行っていくうえで、許認可取得などの点で、政府当局とのコミュニケーションが重要になってきます(賄賂を支払うという意味ではありません)。このような場合に、信頼でき、かつインドネシアで有力なパートナーの協力を得られれば、円滑に事業を行うことが可能となります。
政府当局とのコミュニケーションが必要とされる一例をあげると、税務当局との関係があります。
現在、インドネシア 政府の歳入不足を補うため、税務当局は、徴税強化方針の下、目先の歳入を増やすため強権的に不適切・違法な課税を断行しているようです。(そのため、いったん納税の上で、税務訴訟まで行えば、概ね勝訴により還付を受けているとのことです。)このような場面において、独資の外資系企業が、標的にされているとの見方もあります。
・インドネシア人パートナーの知識・経験や人脈の利用
また、インドネシアの商慣習を取り入れたり、取引先を開拓する際に、インドネシア人パートナーの知識・経験や人脈が必要となりますが、株主として自分の会社であるとの意識をインドネシア人パートナーに与えることができれば、より積極的に協力してもらえることでしょう。
インドネシア人パートナーを、インドネシア法人の株主にむかえ、一定のエクイティを持たせて、共同事業を行っていくことが、インドネシアで円滑にビジネスを行っていく上では、大切であると感じています。
以上のとおり、リスクは当然にあるものの、インドネシアでビジネスを行っていく上では、インドネシア人パートナーを株主として合弁会社を設立するメリットは大きいと思います。
そして、合弁会社を設立する際には、インドネシア人パートナーとの権利義務の確認・整理、相互の役割分担を明確にし、将来のトラブルを防止するために、適切な合弁契約を締結することが不可欠になります。合弁契約については、別途記事を書きたいと思います。
※上記は、筆者の見解を交えた説明であり、個別事例への適用については一切の責任を負えません。個別の案件に関しては、別途ご相談ください。
弁護士 味村祐作
P.S. 写真は、東ヌサ・トゥンガラ州アロール島近海にて撮影。










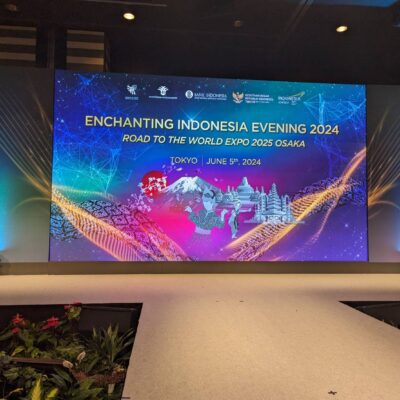






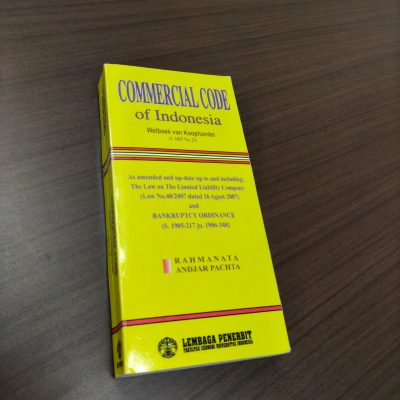
この記事へのコメントはありません。